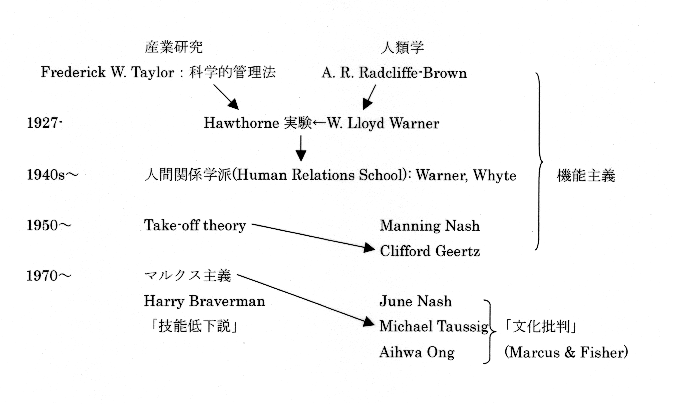E-1. 森田 敦郎(東京大学大学院)
近代的産業における組織・労働・技能の人類学
〈はじめに〉
本来、未開社会の研究として誕生した人類学が、近代社会を研究することは可能なのだろうか。本論文では、産業をめぐる諸問題に注目して、人類学が近代的な現象を研究する方法論を考察する。
〈学説史〉
人類学における産業研究の歴史は以下の図のとおりであり、他の分野と密接に関わりながら発展してきた。この分野においては、機能主義と「文化批判」が主要な対立する陣営であった。
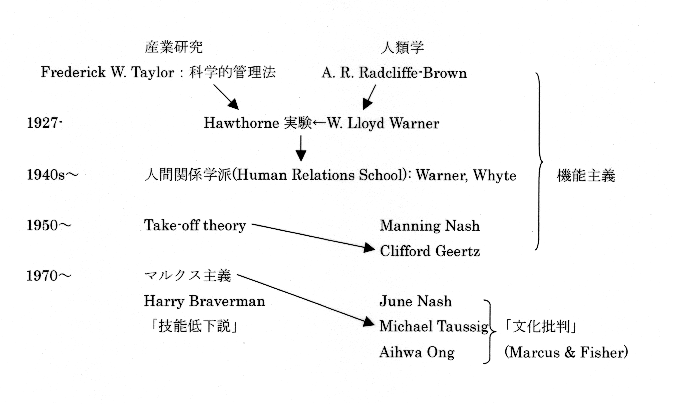
しかしながら両者はともに、近代産業では労働は社会関係から切り離されているという前提を共有してきた。かれらは、生産の技術的関係と社会関係を切り離し、前者が生産の組織を支配しているという技術決定論的なモデルを採用していた。
〈民族誌事例の再検討〉
本論文ではこうした潮流に対して、いくつかの民族誌的事例(コピー機修理工、製鋼所など)を挙げながら次のような反論を行う。第一に、詳細な職場の民族誌によれば、近代的産業においても労働者の社会関係が、情報の伝達や不確実性への対処に際して極めて重要な役割を果たしている。第二に、多くの人類学者は労働者を比較的均一な集団と見なしてきたが、実際の労働者は熟練度、職種、コミュニティとの関係などによって複雑に分化している。産業における変動や紛争を理解するためには、これらのサブ・グループ間の関係を捉える必要がある。
〈産業の生態学〉
その上で本論文では、「産業の生態学」という新しいアプローチを提案する。これは、従来の静態的で技術決定論的な産業モデルに代わるもので、以下の枠組みからなっている。(1)産業組織の中で行われる活動(=タスク)と、これを処理するために人々が創り出すネットワーク(実践的活動のユニット)を分析単位とする。(2)産業組織を、アドホックに形成される実践的活動のユニットの連合体と、固定化された公式の分業の構造(職位制、職権の設定)によって構成されているとみなす。(3)その際、実践的活動のユニットの形成に影響を与える、公式の構造と労働者のサブグループ間の関係に注目する。
このようなアプローチを用いることによって、人類学は近代的産業をこれまでの生業研究と比較可能な形で扱うことが可能になると思われる。
E-2. 飯高 伸五(東京都立大学大学院社会科学研究科)
抱合される首長、離脱する地域社会――パラオ近代における独・日・米統治の拮抗関係と政治組織の再編成
植民地言説を流用する対象社会の戦略性や創造性を主題とする「文化の客体化」論や、「伝統の政治」論では、分析対象が研究者によって恣意的に選択された言説に偏重し、対象社会を構成する一部の人々によって客体化され、操作される伝統やアイデンティティが一枚岩に扱われて社会全体の説明に代えられる傾向がある。そのため対象社会の全体的な分析が放棄され、多様な行為主体の間の葛藤が後背に退く危険性が存在する。本論ではミクロネシア地域パラオ社会の植民地統治過程における政治組織の再編成を検討することで、近年の人類学的植民地研究におけるこれらの問題点に対処しようと試みた。植民地統治以前、パラオ社会の基本的な政治的単位は村落レベルにあり、首長会議が村落政治を運営していた。村落がいくつか集まると村落連合が形成され、村落連合はパラオ全体を二分する村落連合同盟へと関連づけられた。この二大同盟は、西はコロールの首長アイバドル、東はマルキヨクの首長ルクライによって率いられていた。しかし村落連合や村落連合同盟は、主として戦争時などに一時的に顕在化する単位であり、恒常的な中央調節期間は存在しなかった。また首長の権力自体も、他の称号継承候補者との競合性に体現される平等主義的実践や、年齢集団の活動および親族集団の年長女性による称号継承への介入などによって相殺され、複雑な権力均衡のシステムが保たれていた。しかし、植民地政策の中でパラオ社会の政治は中心化を余儀なくされた。19世紀後半以降のドイツ、日本、アメリカの植民地統治時代には、首長やパラオ人の新しいエリートが植民地行政の中に抱合されながら、植民地統治以前に基本的な政治的単位であった村落を飛び越えるような形で、村落連合や村落連合同盟に対して行政制度上の重要性が付与されていった。それらは制度として機能する中で従来よりも実体性をおび、近現代パラオ政治の一部分になった。そしてアメリカ統治下で選挙制度が導入されると、選出される政治家と高位の首長とが対比され、後者が正統な「伝統」の担い手として客体化された。首長たち自身も植民地主義の枠組みを流用しながら、議会に対抗するかたちでパラオ全体レベルの首長会議を組織し、植民地期に公的な土地と分類された土地の返還を求める主張を行った。そして現在、パラオ憲法で成文化されている「伝統」とは、この全パラオレベルの首長会議やそれを構成する村落連合の首長のことである。しかし、植民地言説との対立・流用・連携を経て客体化された政治的伝統がパラオ社会のすべてを包摂したわけではなかった。植民地統治に接続した首長と地域社会の首長とが区別される二元的首長制、依然活発な地域社会の政治的現実、パラオ女性会議の首長会議への抵抗などから浮かび上がってくるパラオ社会の姿は、様々な行為主体が「伝統」や「近代」を様々に使い分ける選択的な柔軟性であった。
E-3. 松田 望美(埼玉大学大学院文化科学研究科)
人間としての胎児−妊娠経験者の語りから−
本研究は胎児がどのように人間となっていくのか、またその際の基準とは何かを妊娠経験者の語りから捉えようとするものである。今日の日本において人間の始まりに対する問いは主に胎児への生殖技術の適用をめぐって発せられるが、この俎上にのせられるのは生物学的なヒトを基盤とした整合的な胎児像であり、その胎児に生殖技術の適用時期を定めるための線引きが人間の基準とされている。生物学以外の側面から胎児を規定する基盤の弱体化が指摘される現在、胎児像を把握する一つの方法として妊婦との関係性に着目し、経験されたものとしての胎児像における人間の基準を考察した。
妊娠経験者22名に聞き取り調査を行った結果、胎児は妊娠が進行するにつれ漠然とした状態から徐々に個別的・具体的存在へと変化するものとして語りに表れていた。変化のきっかけとなるのはからだの変調、超音波診断画像、周囲の指摘、雑誌の解説や体験談などであるが、これらを様々に組み合わせ各人が独自の胎児像を構築している。構築された胎児像は調査対象者との相互作用という点で、人間との連続性の強い存在と不連続性の強い存在の二種類に大別できる。連続性が強い胎児とは胎児期から既に意思や情動が発現、母親との相互作用が開始されまたそれらを通じて徐々に母親の中で「自分の子」としての認識が高まる存在であり、不連続性の強い胎児とは意思や情動が見いだせずまた存在に対する異質感が強く、出生を経てはじめて「自分の子」とみなされるような胎児である。
この連続性・不連続性を手がかりに考察すると、経験という領域において胎児を人間としてみなすということは自己との関係において胎児を受容することと結びついており、胎児に人間との類似点を見出すことを経て、自己との関係に存在を組み込んでいるといえる。よってこの領域における人間の基準は出生と死亡ではなく、胎児期から既に始まりおそらくは死後もある程度持続する、自己と対象となる存在とのつながり感であるということができるが、この基準は線引きとしてではなく、濃度の問題としてみなすことができる。なおこのつながり感という基準において人間の前段階に位置づけられるのは胎児ではなく、未だ関係に組み込まれていないような個別性が薄い存在である。これらをふまえ調査対象者に経験された胎児を人間との関係において捉えると、それは人間の濃度が徐々に高くなっていく過程にある存在だということができる。
このように新たな人間の基準としてつながり感を提出したが、この基準を用いることにより胎児に続く存在である乳児や幼児の人間度や、人間の前段階としての霊魂観などを検討していく可能性が生じたといえる。
E-4. 宮坂 清(慶應義塾大学大学院社会学研究科)
北インド、ラダック地方のチベット系社会の医療人類学的考察 ―巫者ラバ・ラモを事例として―
本論の考察対象は、北インド、ラダック地方のチベット系社会に生きる民間巫者ラバ・ラモ(それぞれ男性巫者・女性巫者)であり、その目的は、彼らの成巫過程や病気治しの儀礼をチベット仏教医学の病い観に基づいて考察することにある。ラバ・ラモは他の医療手段においては解決しなかった自らの病いが仏教の高僧が行う卜占によって巫病であると認められた後、修行を始める。その卜占の説明は「心身を患っているのは神と悪魔が分離しないまま彼/彼女に宿ったためであり、それは巫者になりなさいという神意である」というものである。先輩ラバ・ラモのもとで儀礼に参加しながら行われる修行を通じて、彼らは自らのなかで展開されている神と悪魔の闘いを統御する技術を学ぶ。彼らは儀礼において憑依状態に入った後、依頼者の依頼に応じて卜占や悪魔祓いを行ったり、あるいはもっと直接的に病者の患部に吸いついて病根とされる黒い塊や液体を吸い出したりする。病いの原因が、体の中から吸い出される塊(=悪魔)にあるという依頼者に対するラバ・ラモの説明と、神が宿ったためであるというラバ・ラモの巫病に対する高僧の説明は、仏教の象徴体系に基づく同じ病い説明モデルのヴァリエーションとして解釈できる。彼らの「医療」のベースになっているのは、治す者が治される者でもあり、治される者が治す者でもあるような相互に作用を及ぼしあう関係である。それはチベット仏教医学によって裏づけられる。チベット仏教医学の重要経典『ギュ―・シ』によれば、あらゆる病いのたった一つの原因は「無我の意味を理解しないことに起因する無知」であり、身体を持ってこの世に存在しているかぎり病いから逃れることはできない。生はそのものがすなわち病いであり、病いはただ飼いならし、つきあっていくことができるだけである。そして、そのつきあいかたは、チベット仏教のパンテオンのなかの数多くの神々を使って、仏教そのものによって演出されている。儀礼を長い間行わないでいると再び「巫病」と同じ状態に陥ってしまうラバ・ラモたちの生き方は、生がすなわち病いであるという考え方が具体的にはどのようなものであるのかを示唆する材料となる。彼らの成巫過程から読み取れるのは、病いから健康への移行を目指す西洋医学的な医療ではなく、むしろ生涯を通じて他者との関係のうちに自らの病いを定位しそれを演じ続けるという医療のかたちである。儀礼において巫者は依頼者の演劇空間に参入し、一緒に「病いが治る」という演劇を演じ一緒に苦しむ役回りである。そのようにして依頼者とともに病いが治癒するという物語を演じつづけることは、巫者自身の病いを治癒させつづけるということでもあり、したがって、「治療者」としてのラバ・ラモは生涯「患者」でありつづけるというそのことによって治療者たりえているような存在であるということができる。